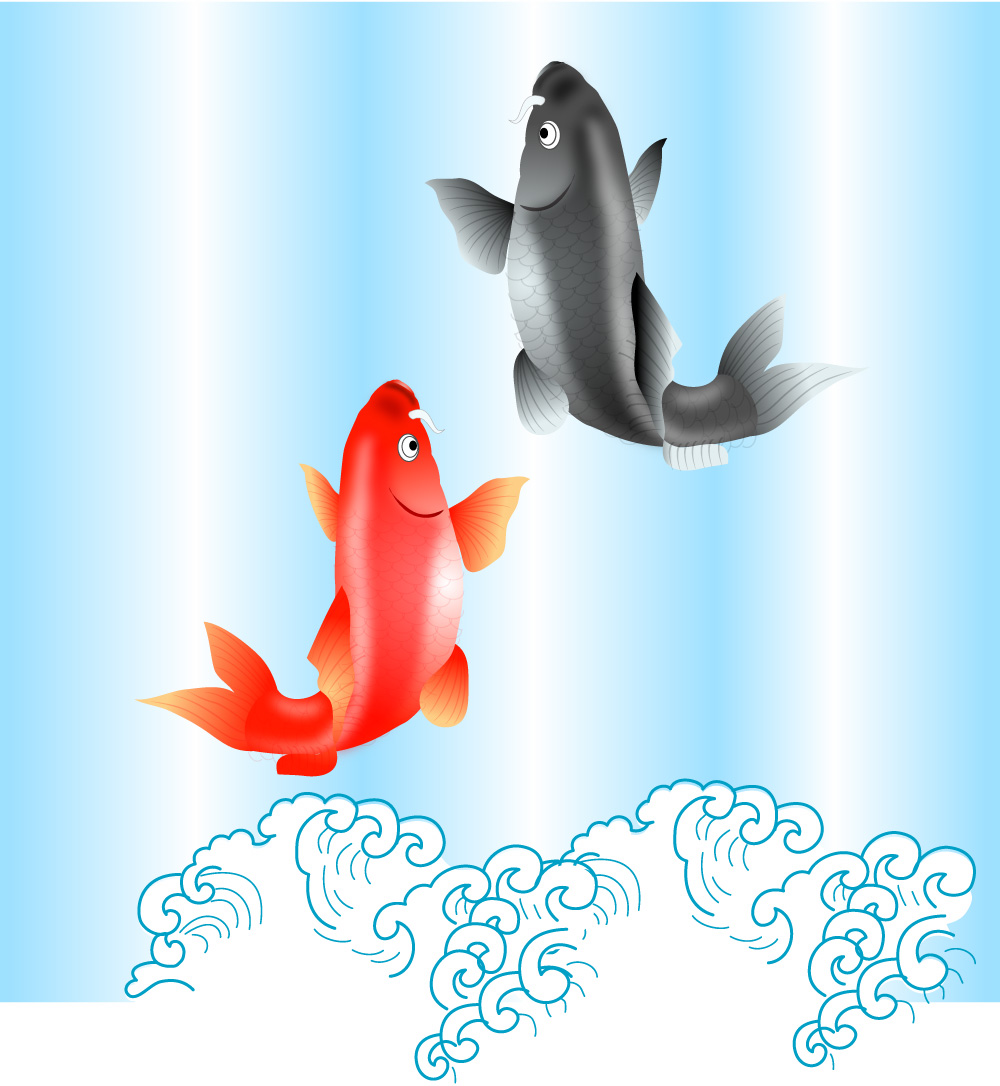その昔、山西省、江西省の省境を流れる黄河の氾濫をくい止めた功績を認められた「う」は後に「夏」という国(この国は殷の前にできた国だから三千五百年以上も前の話)を建てたが、彼が治水した黄河の急タン(竜門)を遡った鯉が昇天し龍になったという伝説があります。この伝説から後漢の終わりころ出世する関門を登竜門と呼ぶようになり、鯉は縁起の良い魚となりました。
「川魚の長」といわれる鯉は、日本人にとって昔からめでたい魚。祝儀の席には必ず出たものでした。鯉の別称を六々魚と言い、中国に「六々変じて九々鱗となる」という諺があります。「中国大陸を流れる黄河は、その源を遠く崑崙山脈の奥に発し、積石山を経て竜門に至る。奔流すこぶる急で、鯉のみが見事竜門を登り、九々鱗つまり竜になるという」・・・有名な登竜門伝説のことです。
これが古くから日本にも伝えられ、鯉にあやかって男の子の節句に、鯉のぼりが立てられるようになりました。また鯉は決して共食いしない習性も、日本では縁起ものとして重宝されている理由です